昨年末は木村拓哉さん主演のドラマ「グランメゾン東京」にドハマりしていたのですけど、シェフが料理の監修をされていた「カンテサンス」の予約が取れたので幸運にも放送期間中にお邪魔することができました。

作品内に登場するお料理がお店で実際に提供されているものだったりして、毎週日曜日がくるごとにカンテサンス欲が高まっていたのですよね。
そして結論から言うと、
「三ツ星を取ろうと思ったら、自分で本物を生み出すしかねえんだよ」
「努力しようがしまいがそんなの関係ないもんな、美味いものさえ作れれば。だけど、みんなそれがなかなかできないから世界中の料理人は必死になって料理のことを考えている」
みたいなセリフが食べている間に思い起こされましたし、最終回まで観終えた今振り返ると、シンクロするところが多々あって、第12話を見たような満足感と幸福感に満ちた食体験になりました。
というわけで、以下ドラマの場面やセリフを散りばめながら振り返ります。

ちなみにカンテサンスのダイニング(客席)は写真撮影が完全NGですが、個室のみ許されているのですよね。
幸運というのは重なるもので、この日は個室でした。

まず忘れないうちに申し上げておきたいのはサービスの方ひとりひとりの素晴らしさ。
尾花シェフがコンソメの作り方を説明しながら芹田くんに「卵白は何のために使うんだっけ?」と聞くシーンがあって、感心した記憶があるのですけど(しかも木村さんのアドリブだったとか!)。
カンテサンスで食事をしていて驚くのは、サービスの方ひとりひとりが出すお料理について「記憶」ではなく「理解」していること。
何を質問しても「シェフに確認します!」ではなくて、それぞれの言葉で説明する姿に余裕さえ感じられます。

ソフトドリンクはジュースもありましたが、せっかくなので台湾茶をいただきます。
お料理はアミューズ、前菜5皿、メイン2皿、デザート3皿、アイスの全12皿。

こちらはお店の名物でもあるカルト・ブランシュ。
分厚い表紙のメニューを開くと、中身は"白紙のメニュー"なのです。
その日にあるいい食材で、その人に合わせて作るので、あらかじめ決まったメニューを作らないというお店の方針を表現しています。
この辺り、グランメゾン東京でのコンセプトにも通ずるところがありましたよね。

アミューズは、アーモンドパウダーのサブレの上に明石の蛸、ひも唐辛子とキノコのマリネ。
サブレとタコという、味も食感も想像のつかない組み合わせ。

想像したよりタコがメインで、後からバターとアーモンド、そしてマリネの香りが追ってきます。
強く味を付けすぎないで、コースの始まりとして食欲を引き出してくれる1品です。

最初の前菜は温かいスープ。
タルトゥーボ、トマト、ビーフ、ベーコン、ハチノス、ブイヨン。
タルトゥーボというのは紫のチコリのようなお野菜だそう。

スープとはいっても具沢山、というかほぼ具。
イメージとしてはおじやを食べているようなスープと具のバランスですね。

表面から見えている分には"野菜たっぷりスープ"に見えたのですけど、ひと口食べると動物性の旨みの濃縮感に驚きます。
ベーコンやビーフ、ブイヨンがベースになっているそうです。
これまた味付けしすぎず、胃袋が温まる1品。
旨み推しで、分かりやすい美味しさでした。

パンは軽く酸味のあるもの。
ここまで、最初は指でつまむアミューズ、次にスプーンを使うスープが出たわけですが…

僕の正面の方は「左利き」だったのですけど、スッと左側にスプーンをサーブするスマートさたるや。
「我々が見るべきは皿ではなくて人なんだ」
これは、京野さんが第8話でレストランのサービスの本質に気付いたときのセリフ。
サービスの方はお料理を出してからお皿を下げにくるまで、客の姿は見えていなかったと思うのですけど、どこかのタイミングで抜け目なく確認されていたのですね…。

るり渓谷ヤギ農園の山羊のミルクで作ったバヴァロワ、フランス・プロヴァンスのオリーブオイル、ゲランドの塩。
上にはマカダミアナッツとゆり根。
できるだけかき混ぜないで食べるように一言添えられます。

いわゆる山羊の香りは皆無で、強い旨みと酸味の立ったバヴァロワは、鮮烈な塩がかかることで甘みも引き出されます。
かと思うと、角が立たないようにまとめ上げる重厚なオリーブオイル。
ゆり根とマカダミアナッツは、食感に似たところがありつつ、やっぱり全然違うので、口に入れてからそれぞれの存在に気付くまでに魔法のような感覚を味わえます。

真鱈の白子のポッシェ ショーフロワ。
軽く火入れしたたら白子の上にホワイトセロリ、モロッコインゲンやフヌイユのサラダ。
下には香箱蟹のほぐし身と内子、そして冷たいブイヨンを注いであります。

ドラマでは第9話で栞奈さんが、「香ばしいものを入れて苦みを強めれば、ワインの甘さをもっと引き出すことができる」とコメントしたお料理でしたが、その後改良されてローストしたピーカンナッツが加えられたバージョンになっています。
冷たいブイヨンに白子と蟹身に、ピーカンナッツという組み合わせが鮮烈。

細かく刻んだホワイトセロリ、セルフィーユも香りが立って存在感十分。
そこへ白子と蟹をクールブイヨンでまとめてある時点で「俺の料理、あそこまで酷評した奴いないからね」という尾花さんのセリフも納得の凄味を感じる1皿でした。

牛の胃袋・ミノのグリエ、上にはブロッコリースプラウトのサラダ。
ドラマ内では、厨房でミノを網焼きしていましたね。

ドラマでは味覚障害のある尾花さんの師匠・潮さんが食べる際に、香りを強くするため「レモンバーム」というハーブを足すシーンがありましたが、こちらはレモンの皮。
酸味が入らないように、果汁ではなく皮で香りを付けるのがポイントだそうです。

レモンの香りに加えて、ホルモンの脂が焼けた香りがしているので、個室内の香りは焼肉店のそれ。
厚みがあって食感にボリュームのあるミノも、細かく刻んだサラダと食べるとどこか上品な印象になっています。

タルトブーダン。
りんごのタルトの上に、ブーダンノワール(豚の血)のペーストとフォアグラのソテー。

ドラマは国産食材にこだわっていたのでここに鶏白レバーの使っていましたが、お店ではフォアグラ。
国内にも美味しい食材はたくさんあって、岸田シェフも積極的に色々な食材を取り入れていらっしゃるイメージがありますが、この辺はやはり敵わないということなのかも。
これだけこだわっている方の選んだものとあっては、ただただ説得力があります。

ドラマの公式サイトにあるシェフの料理解説に書いてある「狙い」を引用すると、
「ブーダンノワールは、すごくクセのある食べ物なので、りんごと一緒に食べるんですけれど、ブーダンノワールと交互に食べていくと、人によって量のバランスが出てくるんじゃないかと思いました」
「どこから切ろうと比率は常に僕が思う完璧な比率。お客様がどんな食べ方をしても必ず完璧な比率で食べられるというのを目指して作った創作料理です」
なるほど、面白い。
左から順番にいただいて、フォアグラで締めます。

サワラのポワレ。
「シェフは火入れに思い入れがあるので、こればかりは他の料理人に触らせないで自信でやっています」
という説明がカッコよかったので、この日以来色々なところで紹介しようとするのですけど「サワラせないで」のところで「ダジャレ?」と言われて上手く話しきれたことがないことも念のため申し添えておきます。

皮目をガッと焼き付けて、皮から伝わる温度を計算した上で、身の側はサッと火を入れるそう。
カンテサンスさんの魚調理のポイントは、塊で焼いてから1人分ずつにカットすること。

日本料理に関する本で、「良い食材はまず生で食べることを考える。生で食べられないとき初めて、加熱する調理を考える」みたいなことを読んだことがあるのですけど、やっぱり日本人にとってこの「ナマ」の質感というのはフランス料理であっても求めてしまうところな気がします。
かといって魚の脂というのは、火が入ってナンボだったりもするので、この皮目の香りというのは生では得難いものです。
ドラマでも様々な調理法を試す描写がありましたが、試行錯誤の末にたどり着いたバランスなのだと思います。

キノコのソースに水晶文旦。
生クリームを少し使っているので、コクがあって爽やか。
この文旦の粒をほぐすところに、若手料理人の苦労が詰まっているようです。
そう思うと、1粒残らず食べたくなる…。

マコモダケ、ニンニク芽、ニンニクとアンチョビ、トマト。
油と相性のいいマコモダケは、やはりたっぷり油を吸った仕上がり。
ニンニクやアンチョビといった、分かりやすく「ウマい」と言いたくなる風味と合わせてあります。

ペルスヴァルのナイフ。
フランスで星付きシェフだった料理人が、自身のスペシャリテである鴨を美味しく食べてもらうため、よく切れるナイフの開発に取り組んだ結果、のめり込んで料理人を辞めナイフ職人になった方が作っているものらしいです。
「この後、鴨が出ます」
と言われたら楽しみにならないわけがありません。

シャラン鴨のロースト。
外から火を入れるので、中まで火を通そうと思うと表面は固くなってしまうわけですが、それを避けるため「1分間オーブンに入れたら、4分間外に出して休ませる」という工程を4時間、つまり48セット繰り返すそうです。
ナイフ職人の方もすごいなと思いましたが、こっちはこっちで大概だな!と思わず笑ってしまうほどのこだわりよう。

でも確かに見るからに違うのですよね…。
お肉が沸騰しているかのように、内側からじゅわじゅわとあふれ出続ける肉汁。
加熱されて旨みが出ているのにやわらかい、それでいて歯応えはある。
得も言われぬ逸品でした。

ピーナッツとセロリのフリット。
上に乗っているのは香味野菜を刻んだソース。

ソースはちょっと意外性があって、シェフが好きで持っているオールドカンパリを使ったという甘酸っぱいソース。
もっと重かったり、しっかり甘いソースを合わせたりしそうなものですが、サラッと軽いものにしているのは、コース全体の分量などを考えてのことなのだそうです。
確かにここまで振り返ると、品数が多い一方で、印象として重い料理というとタルトブーダンくらいだったように思います。

ただ美味しい料理を作るだけでも大変なのに、ただ美味しければいいだけではなくコースとしてバランスのいいものにしなければいけない、というところにまで思いが致された極上の食事。
こちらが質問したから教えてくださってはいますが、実際には客側に気付かれないように、気付かれないとしてもここまでこだわり抜く料理人の仕事に切なさすら感じて気が遠くなります。
そしてこの後デザート。
「料理なめんなよ」と後輩の松井さんに言い放った平古くんの言葉は、
「フレンチレストランのデザートは、コースを構成する料理のひとつだ。しかも最後を締めくくる重要な役割がある」「プロの料理人たちが結集して、アイディアを出し合って何度も失敗してやっとたどり着いた珠玉のコースだよ。この化け物みたいな料理の後に、こんなリキュールまみれの甘ったるいモンブランなんか出せるわけないだろ」
と続きました。
さて、ここからデセール3皿です。

まずは冷たいデセール。
ここで口直し程度のシンプルなソルベが出されるケースが多いように思いますが、カンテサンスでは重くならない範囲でいくつもの要素を入れ込んであります。

洋梨のソルベ、新高のキャラメリゼ、早摘みぶどう(ヴェルデ)のグラニテ。
食感と味の変化、果肉を入れることで口の中の温度が一旦落ち着くので、ちゃんと味を感じることができるようになっていると思います。

アクセントにきゅんきゅんくるような酸味が入るので何かと思ったのですけど、ぶどうのグラニテが散りばめられている効果のようでした。
1品目から引き込まれるデセールでした。

続いては黒イチジク。
下にマスカルポーネとイチジクのソルベ。

イチジクはスライスして1枚ずつキャラメリゼ。
デセールの構成としては、素材と素材の組み合わせだけで味わうようなもので、確かに「リキュールまみれの甘ったるい」ソレとは一線を画したところに満足感があるものですね。

最後のメインとなるデセールは…!!おお!!!
モンブラ…と思ったら、

「チュロス、かぼちゃのペースト、メイプルシロップのクリーム」という説明があって、栗が出てこないのですね。
何でも「栗を使わないモンブラン風のデセール」なのだとか。
てっきりモンブランと勘違いして一度歓声を上げてしまった我々を気遣ってか、
「かぼちゃは、栗かぼちゃでございます」
という説明に大笑いでした。

下からチュロス、栗かぼちゃのペースト、メイプルシロップのクリーム。

フルーティーなデセールが2品続いたところで、素朴でどっしりとした味にまとめたこの1品。

カットしてみると、チュロスが「もふっ」と非常にソフトな質感なので「いつ焼いたんですか?」とお聞きすると、なんと揚げたてを使っているのだとか。
そういえば以前いただいたタルトも焼きたてをオーブンから出したまま提供すると伺ったように思います。
揚げの香ばしい甘みをベースに、かぼちゃの落ち着いた風味とほんのりメイプルシロップの香り。
尖ったところがあるわけではないものの、記憶に残る1品でした。

最後にスペシャリテのメレンゲのアイス。
スプレーで能登の海水を吹き付けて提供されます。

スプーンを挿し込んでまず驚くのはムースにも近いようなやわらかさ。
キャラメルほどではないものの、香ばしさのある甘み、海水の塩気とのコントラストでコク。
13年間三ツ星を獲り続けるお店が、変わらず提供している理由の分かる、シンプルながら完全無欠なアイスでした。

シェフの料理解説を読んでいたら、
「今回『マグロ』のテーマをいただいたとき、『僕はマグロを守っている身なので、そのテーマは辞めたい』と言い続けてきました」
という一文があって、さらに、マグロを使う代わりに
「太平洋マグロ(いわゆる日本の近海のマグロ)は使わずに、大西洋マグロ(ヨーロッパやアメリカ、インドなど遠洋にいるマグロ)を使う」
というセリフが追加されたというエピソードが明かされていました。

お茶菓子のディアマン。
岸田シェフは、今回の監修の仕事を引き受けた背景として「人手不足に陥っている料理の世界の魅力を改めて発信したい」という思いがあったそうですが、これはただ「料理人を志す若者が増えるように」という意味だと思っていました。
それがマグロの件のように、シェフの思いがここまでドラマのセリフにも反映されていることを考えると、尾花さんが平古くんに言った、
「フレンチ辞めんじゃねえぞ」
という一言などは、既に料理業界で働く後輩たちに向けて、苦しくても続けようという叱咤激励だったのではないかという気もしてきています。
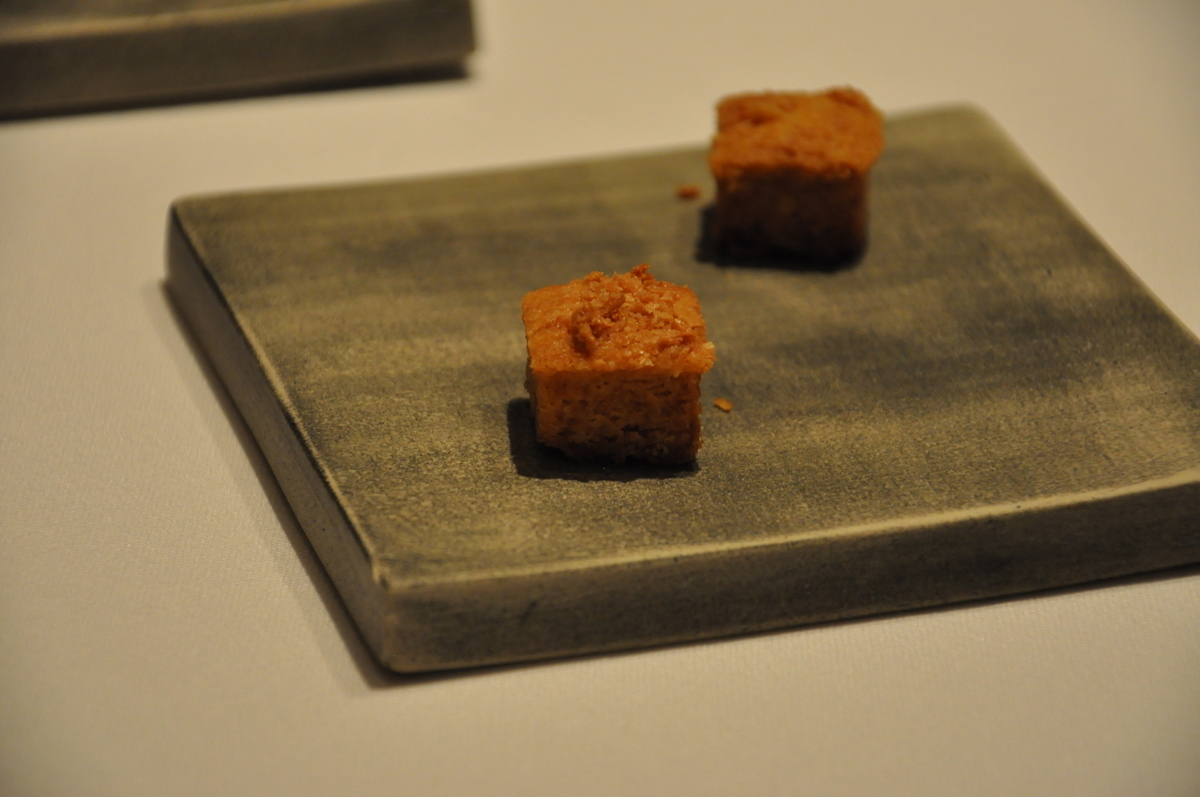
新規参入者を増やしたいだけなら、若者のサクセスストーリーにすればいいものを、「49歳」の「女性シェフ」が最終回で「あんなこと(一応ネタバレ回避)」になるというドラマにしたのは、やっぱり料理人たちの胸に希望の火を灯したかったのかなという気がして、今改めてグッときているところです。
セリフや動作、小道具など細部に至るまで本物を追求されたドラマで、最終回まで観終えて改めて気付くこともありそうなので、機会をみつけて全部観返したいなと思っています。
何だか結局ドラマの感想みたいになってきてしまいましたが、星もドラマも関係なく、ただただ素晴らしいお店、食体験ができました。
そしてお料理どれも「バカ美味えな」でした!ごちそう様でした!